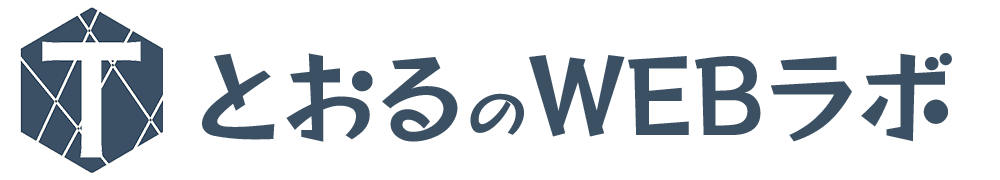はじめに
「フリーランスになりたいけれど、何から始めればいいのかわからない」という人はとても多いです。フリーランスという働き方は魅力的ですが、自由と引き換えに、準備や知識が必要になります。
ここからは、「フリーランスになるには?」という疑問に答えるために、実際に独立する前に知っておきたい5つのポイントを丁寧に紹介していきます。
現役エンジニアに増えている「フリーランス志向」
最近では、会社に属さず自由に働く「フリーランス」という働き方を選ぶエンジニアが増えています。特にIT業界では、在宅勤務や副業解禁の流れもあり、会社に縛られず自分のスキルで稼ぐことに魅力を感じる人が多くなっています。
自分の時間を自由に使える、好きな仕事を選べる、収入の上限がないといった理由から「自由な働き方」として注目されています。一方で、収入が不安定になったり、仕事とプライベートの境界が曖昧になったり、健康管理やスキルアップもすべて自分で行う必要があるなど、自己責任の重さも避けては通れません。
「自分もいつかフリーランスに」と考えているものの、「実際どんな準備が必要なの?」「自分にもできるの?」という不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事の目的と想定読者
この記事は、「フリーランス なるには?」という疑問を持っている現役のコーダーやエンジニアに向けて書かれています。フリーランスとして独立するために最低限知っておくべき5つの基本ポイントを、実体験も交えながらわかりやすく解説します。
これからフリーランスを目指す方が、準備不足で後悔することがないように。この記事が、あなたの「最初の一歩」を後押しする参考になれば幸いです。
1. フリーランスになるには、まず「開業手続き」が必要
フリーランスとして働き始めるにあたって、まず最初に行うべきなのが「開業手続き」です。
会社を辞めてすぐに案件を取りに行きたくなる気持ちも分かりますが、きちんと法的に個人事業主として登録しておくことで、税制面や信用面で大きなメリットがあります。
このステップを飛ばしてしまうと、後々の確定申告で困るだけでなく、経費計上や契約上のトラブルにもつながりかねません。
なぜ開業届が必要なのか?
フリーランスになるには、まず税務署に「開業届」を提出して、個人事業主としての登録を行う必要があります。これにより、事業としての収入が「事業所得」として認められ、所得の種類に応じた控除や、青色申告による最大65万円の特別控除といった税制上のメリットを受けることができます。
また、フリーランスとして仕事をする際に「事業として行っている」という証明にもなり、クライアントや取引先に信頼感を与えることができます。特に、法人や大手企業との契約時には、開業届の提出が前提条件になるケースも少なくありません。
開業に必要な書類と手続き方法
開業の際に必要な書類は、主に以下の2つです。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(通称:開業届)
- 青色申告承認申請書(節税を意識するなら提出を推奨)
これらの書類は、税務署の窓口に直接持参するほか、郵送やe-Tax(電子申告)でも提出可能です。最近では、国税庁のホームページからPDFでダウンロードしてそのまま記入できるようになっているため、そこまで手間はかかりません。
ちなみに、提出期限にも注意が必要です。青色申告承認申請書は、開業日から2か月以内に提出しないと、その年から青色申告を適用できないので、開業と同時に提出しておくのがおすすめです。
事業用口座や屋号の準備も忘れずに
開業届の提出とあわせて準備しておきたいのが、事業用の銀行口座やクレジットカードです。プライベートと事業のお金をきっちり分けて管理することで、経理や確定申告が格段に楽になります。
また、開業届には「屋号(やごう)」という事業名を記載する欄があります。これは法人名のようなもので、任意ですがあったほうが信用を得やすくなります。たとえば請求書や名刺に「屋号 + 自分の名前」で記載することで、ビジネスとしての印象を与えることができます。
屋号を設定し、事業用の口座とクレジットカードをすべて専用に切り分けておくことで、帳簿づけや経理作業が格段にスムーズになります。
2. 収入の不安定さを理解しておこう
フリーランスとして独立を考えたとき、多くの人が最初に気になるのが「収入の不安定さ」です。会社員であれば、毎月決まった日に給料が振り込まれ、ボーナスや福利厚生といった安心感があります。一方でフリーランスは、自分で仕事を見つけ、自分で報酬を請求しなければ収入が発生しません。つまり、全てが自己責任の世界に入るということです。
フリーランスは自由度が高い反面、安定性には欠ける働き方とも言えます。しかし、正しい知識と戦略を持っていれば、収入をコントロールし、安定させていくことも可能です。この章では、フリーランスにおける収入の特徴と不安定さの具体例、そしてそれを乗り越えるためのコツについて詳しく解説していきます。
フリーランスの収入の特徴とは?
会社員とは違い、フリーランスには「固定給」という概念がありません。どれだけ働くか、どれだけ受注できるかによって収入が変動します。
- 月によって大きく変動する
- クライアントに左右される
- 働かなければ収入がゼロになる
このような特徴があるため、毎月の生活費や支出を一定に保つには、それなりの計画性とスキルが必要です。また、報酬の支払いが翌月末や翌々月というケースも多く、キャッシュフローの管理も重要になります。
さらに、病気や家庭の事情などで稼働できない期間が発生した場合、即座に収入減へと直結するのもフリーランスの特徴です。そのため、あらかじめ生活防衛資金を確保しておくことも大切です。
よくある収入の不安パターン
実際のフリーランスにありがちな「収入不安の原因」は次のようなものがあります。
- 案件が途切れて収入ゼロになる
- 急にクライアントが契約を打ち切る
- 単価交渉がうまくいかず、稼働が多い割に収入が少ない
- 納期遅れやトラブルで支払いが遅延する
- リピート案件がなく、常に新規営業をし続ける状態になる
特にフリーランス初期は、継続案件を持っていなかったり、クライアントとの関係構築がまだ浅かったりするため、こうしたトラブルに直面する可能性が高まります。
安定化のコツと対策
収入を安定させるためには、受け身ではなく「戦略的な働き方」が欠かせません。以下のような方法でリスクを分散させ、着実な収入を得られる状態を目指しましょう。
- 複数の案件を同時に進行する(1社依存を避ける)
- フリーランスエージェントを活用し、案件の継続性と単価の安定を図る
- 単価交渉や条件確認を怠らず、自分の価値を明確に伝える
- 定期的にスキルアップを行い、市場価値を高める
- 自分のブログやSNSで情報発信をして、直接依頼の導線を作る
- ストック型収入(広告収益・教材販売・サブスク)を育てる
たとえば、ひとつの案件に100%依存している状態では、その契約が終了した途端に収入も途絶えてしまいます。複数の案件や収入源を持っていれば、一つが終わっても他で補える仕組みができます。
また、フリーランスエージェントを利用することで、営業の手間を減らしながら安定した仕事を確保することもできます。案件によっては社会保障サービスが付いているものもあり、フリーランス初心者にも安心感があります。
将来的に、フリーランスとして「安定した自由」を手に入れたいのであれば、こうした工夫を意識しながら、継続的な改善と努力を続けていくことが重要です。
3. スキルの棚卸しと「売れる自分」の明確化
フリーランスとして案件を獲得し続けていくためには、単に「技術がある」だけでは不十分です。自分がどんなスキルを持っていて、どんな案件に対応できるのかを明確に整理し、それを相手に伝えられる状態にしておく必要があります。
自分自身のスキルや実績を棚卸しし、「自分は何ができる人なのか」「どんな価値を提供できるのか」を言語化することは、フリーランスとして働くうえで最初に取り組むべき重要な作業です。この作業をしっかり行っておくと、案件の選定や営業、単価交渉にも自信を持って対応できるようになります。
ここでは、自分のスキルを整理する方法から、ポートフォリオの作り方、そして「選ばれる自分」になるために必要な要素を具体的に解説します。
自分のスキルをどう整理するか?
まずは、これまで自分が身につけてきたスキルをすべて洗い出すところから始めましょう。使用できる言語やフレームワーク、CMS、デザインツール、プロジェクト管理ツールなど、なるべく具体的に書き出します。
「HTML/CSSは〇年経験」「WordPressで10サイト以上構築」「Figmaを使ってUIデザインの提案まで可能」など、経験年数や実績も一緒に整理しておくと、クライアントにも伝わりやすくなります。
また、どんなジャンルの案件を多くこなしてきたのか(例:コーポレートサイト、ECサイト、ランディングページなど)を分類しておくと、自分がどの分野に強いのかも明確になります。
ポートフォリオや実績の見せ方
自分のスキルや経験をただ言葉で説明するだけでなく、目で見てわかる「ポートフォリオ」があると、信頼度が大きくアップします。
WebサイトやGitHubにポートフォリオページを作成し、制作したサイトのスクリーンショット、使用技術、工夫したポイントなどを記載しましょう。可能であれば実際のURLや、クライアントの許可が取れている場合は社名も記載すると効果的です。
デザインが苦手な方でも、テンプレートを使えば見栄えのよいポートフォリオは十分に作成可能です。また、ポートフォリオは一度作って終わりではなく、定期的に更新していくことも重要です。
強み・単価感を明確にする
案件を獲得するには、たくさんのフリーランスの中から「この人にお願いしたい」と思ってもらう必要があります。そのためには、自分の「強み」を明確に言語化し、提案やプロフィールに落とし込んでおくことが大切です。
例えば、「BtoBサイトに強い」「修正対応が早い」「コミュニケーションが丁寧」など、スキル以外の部分も立派な強みです。自分では当たり前と思っていることが、クライアントにとっては安心材料になることもあります。
あわせて、単価についても自分の基準を持っておきましょう。希望単価、最低受注金額、稼働時間あたりの相場などを明確にしておくことで、安請け合いによる消耗を防げます。
自分の価値を正しく把握し、相手にしっかり伝えられるようにしておくことが、安定したフリーランス活動の第一歩になります。
4. 仕事の獲得方法を事前に理解しておく
フリーランスとして収入を得ていくうえで、もっとも重要なのが「仕事の獲得方法」です。会社員であれば、会社が与えてくれる仕事をこなせば給料が支払われますが、フリーランスの場合はそうはいきません。自分から動いて案件を獲得しなければ、収入はゼロのままです。
特に独立初期は、営業経験が少ない、実績がまだ少ない、といった不安もあるかもしれません。ですが今は、初心者でも仕事を獲得しやすい仕組みやサービスも整ってきているため、適切な方法を選べば誰でもスタートを切ることができます。
この章では、代表的な案件獲得方法を紹介しつつ、初心者が最初に取るべき行動、そして特に有効なフリーランスエージェントの活用法について具体的に解説していきます。
案件獲得の主な手段と特徴
- フリーランスエージェント:高単価案件を紹介してくれる。サポートも手厚い。
- クラウドソーシング:初心者でも参入しやすいが、競争が激しく単価は低め。
- SNS・人脈:信頼関係からの紹介で継続案件になりやすい。
- 自分のサイト・ブログ:長期的には案件獲得の自動化が期待できる。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあります。たとえばエージェントは案件の質が高く、サポートも受けられますが、紹介手数料が発生する場合もあります。クラウドソーシングは誰でも参加しやすい一方で、単価の低さや競争の激しさに注意が必要です。
SNSや知人からの紹介で仕事をもらえることもありますが、これは信頼関係があってこそ成立する方法なので、すぐに効果が出るわけではありません。長期的な関係づくりとセットで考える必要があります。
初心者におすすめの方法は?
フリーランスとしての活動を始めたばかりの方におすすめしたいのが、「フリーランスエージェントの活用」です。
エージェントは、登録者に対して希望条件に合った案件を紹介し、営業・契約・交渉などのサポートまで行ってくれます。自分で営業をかける必要がないため、営業が苦手な人でも安心して案件に集中できます。
また、報酬や契約のトラブルが起きにくい点も魅力です。間にエージェントが入ることで、クライアントとのやり取りがスムーズになり、支払いトラブルのリスクも軽減されます。
特に実績がまだ少ないうちは、「○○社の案件に参加した」という事実そのものが次の案件獲得にも有利に働きます。まずは信頼できるエージェントに複数登録してみて、自分に合うサービスを比較してみるのが良いでしょう。
エージェント活用のポイント
- 自分の希望条件(単価・稼働日数・働き方など)を明確に伝える
- 複数のエージェントに登録し、選択肢を広げる
- 定期的に連絡を取り合い、最新案件の情報を得る
- スキルシートやポートフォリオを充実させておく
- エージェント担当者との信頼関係を築く(丁寧なコミュニケーション)
エージェントは、単なる「案件紹介の場」ではなく、長期的なパートナーとして付き合っていける存在です。相談できる担当者がいるだけでも、独立初期の不安は大きく軽減されます。
フリーランスにとって、「仕事を安定して得られる仕組みを持つこと」は非常に重要な課題です。最初はエージェントに頼りながら、徐々にSNSやブログ、人脈といった他の方法にも取り組んでいくと、将来的な安定性も高まっていきます。
5. 保険・税金・年金など「会社がやってくれてたこと」は全部自分で
フリーランスとして独立すると、それまで会社が自動的にやってくれていた手続きや支払いを、すべて自分で行う必要があります。これまで給与から天引きされていた健康保険料や年金、住民税、さらには所得税の申告なども、すべて自己責任になります。
特に会社員時代に意識していなかった人ほど、最初にこの「手続きの多さ」と「知らなかったルール」に戸惑うことが多いです。ですが、これらのことを理解し、早めに準備しておくことで、安心して仕事に集中する環境を整えることができます。
この章では、フリーランスとして必須の手続きや管理すべきこと、そしてそれらを効率よく行うための便利なツールについて紹介します。
自分でやらなければならない主な手続き
フリーランスは、社会保険・年金・税金すべてを自分で管理します。基本的には、会社員時代に給与から差し引かれていたものを、自分で手続きをして納付していく形になります。
- 国民健康保険への加入(または退職後2年間の任意継続)
- 国民年金の加入と月額保険料の支払い
- 所得税・住民税の納付(年に一度の確定申告が必要)
- 消費税の課税事業者に該当する場合は、消費税申告も発生
確定申告では、1年間の売上・経費・利益を集計し、税額を計算して納付します。経費の計上には領収書や明細の保管が必要であり、日頃からの記録が重要です。
また、必要に応じて「小規模企業共済」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」といった制度に加入することで、将来への備えや節税につなげることもできます。会社員時代よりも制度を自分で選び、賢く利用する力が求められます。
会計ソフトの活用も検討しよう
経理や確定申告が不安な人は、クラウド会計ソフトの活用がおすすめです。近年ではフリーランス向けに最適化されたサービスが数多く登場しており、会計知識がなくても簡単に記帳や申告ができるようになっています。
代表的なクラウド会計ソフト:
- Money Forward
- freee
これらを使えば、日々の取引を記録しながら帳簿を自動で作成してくれるほか、請求書の発行や銀行口座との連携も可能です。確定申告時には、集計したデータから必要な申告書類を自動で生成する機能もあり、非常に効率的です。
経理にかかる時間を最小限に抑えつつ、ミスを減らすためにも、早い段階からツールを導入し、使い慣れておくことをおすすめします。
まとめ|フリーランスになるには、準備と覚悟が必要!
この記事では、「フリーランスになるには?」という疑問を持つ方に向けて、独立するために知っておくべき基本的な5つのポイントを紹介してきました。
自由な働き方に憧れる一方で、不安定さや自己管理の難しさに尻込みしてしまうのも自然なことです。しかし、しっかりと準備を重ね、正しい知識を身につけておけば、不安を大きく減らし、フリーランスという道を自信を持って歩むことができます。
以下に、今回お伝えした内容をもう一度おさらいしておきましょう。
本記事のまとめ
- 開業手続きが最初のステップ
- 収入の不安定さは避けられないが、対策はできる
- スキルの棚卸しと自分の価値を言語化する
- 仕事の探し方を知り、準備しておく
- 税金・保険などの手続きを自分でこなす必要がある
これらのステップをひとつずつ着実にクリアしていけば、たとえ今すぐに独立できなかったとしても、数ヶ月後・半年後には十分にスタートラインに立てるはずです。
最後に:フリーランスに必要なのは「情報」と「行動力」
フリーランスになるには、決して簡単な道ではありません。だからこそ、事前に情報を集め、備えをし、少しずつでも行動に移していくことが大切です。
この記事を読んでくださったあなたが、これからの働き方をより前向きに考え、納得できるキャリアを築くための一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。
迷っているなら、まずは小さな一歩から始めてみましょう。